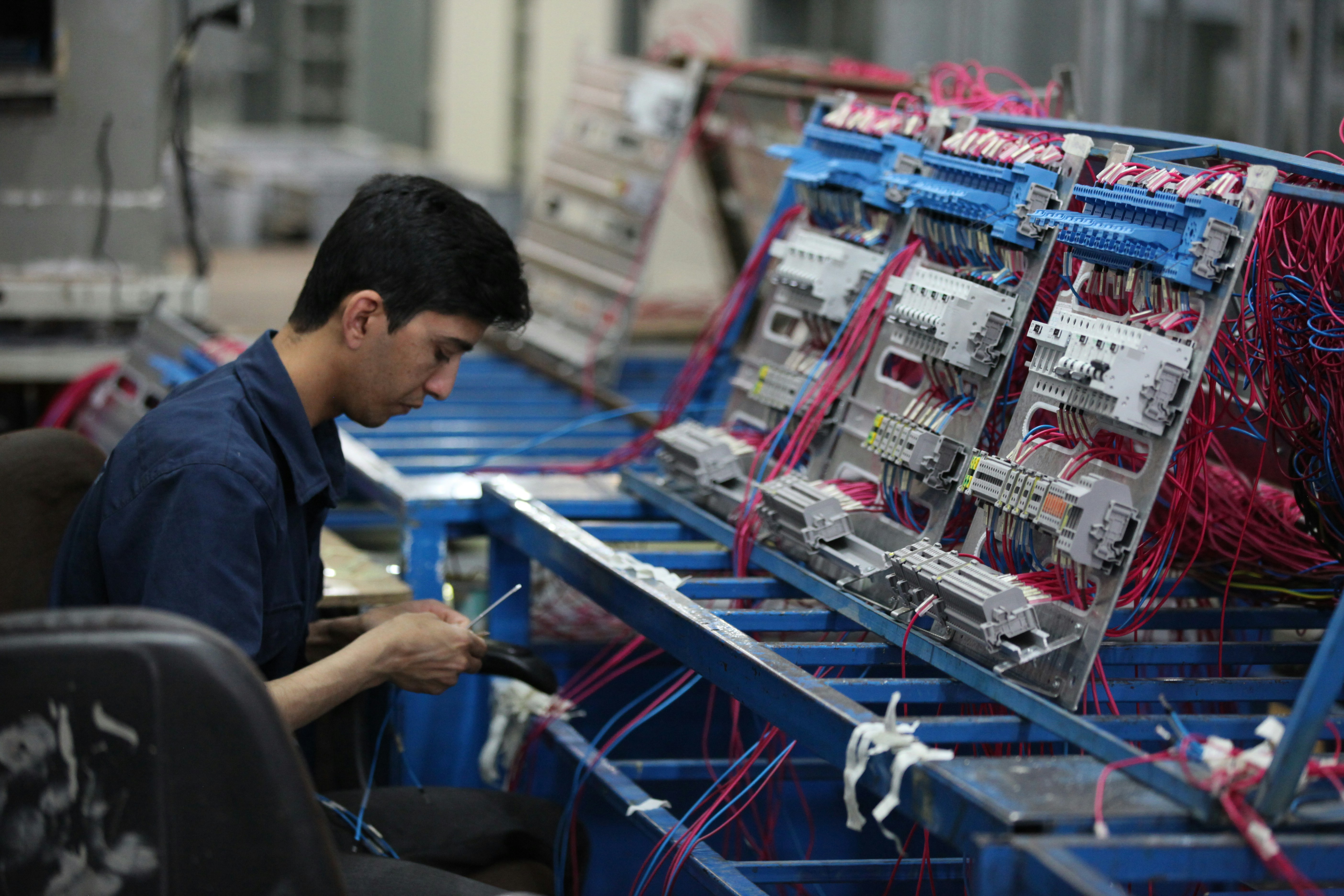
折り畳み型スマホ:中韓メーカーの競争激化、サムスンを中国勢が追撃
世界の折り畳み型スマートフォン市場では、韓国と中国のメーカーが圧倒的な存在感を示しています。市場シェを伸ばすべく、各社が新製品を相次いで投入する流れです。韓国メーカーでは、業界最大手のサムスン電子が折り畳みスマホの新機種「Galaxy Z Fold 7」を投入。中国メーカーでは、HONOR(オナー)が世界最薄の折り畳みスマホ「Magic V5」を発表したほか、華為技術(ファーウェイ)が新たな三つ折りスマホ「Mate XTs」を披露しました。
折り畳みスマホ市場は韓国メーカー(サムスン電子)の独走状態が続いていましたが、中国メーカーの追い上げによって勢力図が変わりつつあります。市場調査会社のデータによると、サムスン電子の世界シェアは2023年の54%から24年に45%まで急低下。ファーウェイなどの猛追によって、足元で中国メーカーに追い抜かれたとの見方も出るほどです。
折り畳み機種がスマホ世界市場に占める割合は、23年時点で1.2%にとどまるものの、27年には同割合が3.5%まで上昇すると予想されるため、中韓メーカーによる折り畳みスマホ市場競争は今後さらに激化していくと思われます。
ASEAN域内イスラム国家:日系ラーメン店の参入加速、ハラル対応が進む
イスラム教徒がブタ肉を使った料理を食べられないにもかかわらず、東南アジア諸国連合(ASEAN)域内のイスラム国家では日系ラーメン店の進出が相次いでいます。ラーメンには豚肉や豚エキスが使用されるケースが多いものの、他の具材で代替するなどイスラム教の戒律に沿った「ハラル認証」食材の導入が進んでいるためです。
最近のニュースでは、ハラル対応の和食店を展開するアセットフロンティア(本社:東京都港区)が8月、アジアを中心に飲食事業を展開するフード・イノベーション・ホールディングス(本社:シンガポール)の現地法人と折半出資でラーメン店運営の合弁会社を設立したと発表。ハラル対応のラーメン店「帆のるラーメン」を展開し、クアラルンプールに1号店を開業したことを明らかにしました。
またラーメン店「一風堂」を展開する力の源ホールディングスも今年6月、インドネシアでハラル対応の店舗をオープンすると発表。豚骨スープを用いず、鶏肉やエビなどを具材やスープに使う形でラーメンを提供する計画を明らかにしています。早ければ9月中にも、首都ジャカルタ近郊で1号店を開業するとのことです。同社はすでにインドネシアで「一風堂」を8店舗展開し、現地の華僑向けに豚骨スープのラーメンを提供していますが、ハラル対応の店舗は今回が初となります。
インバウンドの活況もあって日本のラーメンが世界的な人気食となるなか、イスラム国家では今後もハラル対応ラーメンの需要が拡大していくこととなりそうです。
風力発電は日本で苦戦もASEANに商機、国内撤退の三菱商事がラオスで新規事業
三菱商事は8月27日、千葉県と秋田県の3海域で洋上風力発電所を建設するプロジェクトから撤退する意向を表明しましたが、翌28日には真逆の動きとして、同社などが出資するラオス南部の「モンスーン陸上風力発電所」が商業運転を開始したと発表したのです。
日本国内のプロジェクトから撤退する理由について、三菱商事の中西勝也社長は「2021年に落札して以降、世界的なインフレなどとともに風車メーカーによる値上げなどが重なり、コストが大きく膨らんだ。建設費用が当初見込んだ金額の2倍以上の水準に膨らんだため、事業期間全体での売電収入よりも保守や運転の費用を含めた支出の方が大きくなり、事業計画の実現が困難との結論に至った」と説明。価格破壊といわれた最安値での応札も足を引っ張り、日本国内でビジネスを展開することの難しさを改めて印象付けました。
ただ、日本よりも低コストでプロジェクトが進められ、採算の見通しが立つラオスでは事情が異なります。出力600メガワット(MW)の「モンスーン陸上風力発電所」は、陸上風力発電所として東南アジア諸国連合(ASEAN)域内で最大規模。発電した電力を一大消費地のベトナムにも輸出するため、安定的に事業が継続できる見通しです。
他の日本企業にも、ASEANで風車発電プロジェクトを積極展開する動きが見られます。五洋建設は昨年11月、洋上風力発電の電力ケーブル敷設に使う大型自航式ケーブル敷設船について、シンガポール海洋エンジニアリング会社のパックスオーシャングループに建造を発注したと発表。洋上風力の風車建設工事から、電力ケーブル敷設工事へと事業の幅を広げる計画を打ち出しました。
また総合商社も、ASEAN域内で風力発電を含む再生可能エネルギー事業に取り組んでいます。双日は昨年10月、ベトナム複合企業のタインタインコン(TTC)グループと再生可能エネルギーや農業分野に関する協力覚書(MOU)に調印しました。再エネ分野では太陽光発電や風力発電のほか、持続可能な航空燃料(SAF)の分野で協力を検討します。
